人材の多様化からはじまった働き方改革――そこにあった社長の苦い経験と確かな確信
社内でひときわ存在感のあるアルバイトスタッフのダブルワーク
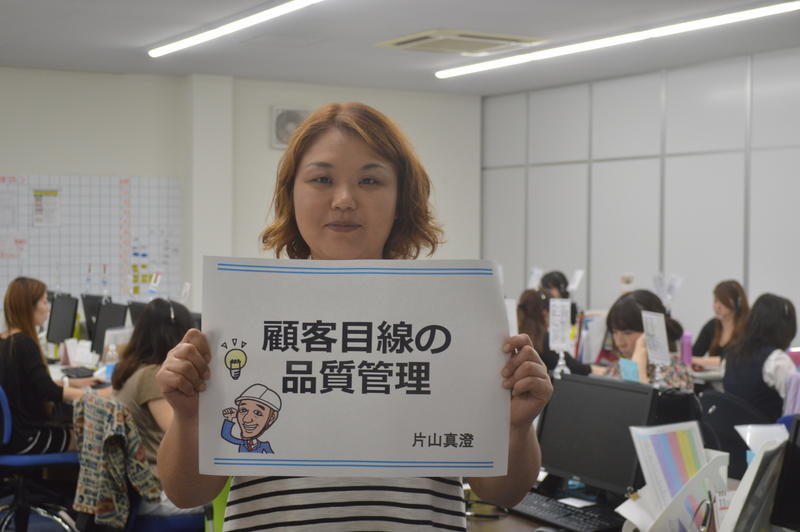
株式会社インターゾーンは、システムの開発事業、コールセンターの事業、Webのマーケティング事業、という3つの事業を展開しています。代表の鏡山健二が2000年に創業して以降、20代の若手独身男性中心に、時間無制限に働くことが当たり前の環境でした。そんなインターゾーンは、2018年現在、時短や週4日勤務の正社員など多様な働き方を採用しています。
これらの新たな取り組みのきっかけとなったのは、コールセンターのアルバイトスタッフでした。
鏡山 「コールセンター事業が拡大しはじめた2013年に、アルバイトスタッフを大量に採用したんです。学生などの若年層から高齢者まで老若男女、多様なバックグラウンドを持つ人たちが入ってきてくれました。その中でとくに多かったのは、育児をしながら働くママたちでした。
彼女たちは、限られた時間しか働くことができないものの、めちゃくちゃ一生懸命で、能力も意欲も正社員に引けを取りませんでした。その中のひとりの、ひときわ存在感のある片山真澄に話を聞くと、シングルマザーとして小学生の子どもを育てながら、昼はコールセンター、夜はカラオケ屋で働いているというんです」
ずっとここで働いてもらいたいーー。当時のインターゾーンには、正社員の時短勤務という前例はありません。しかし、限られた時間の中で一生懸命働く彼女たちのことを全員が認めていました。
たとえ時短であっても、正社員になって別に構わないじゃないかーー。困ることは何もないと確信した社長の鏡山は、彼女たちの社員化をすすめていきました。
そして、それは思わぬところで、幸せな追い風を運んでくれることになります。
鏡山 「当時営業に配属された新卒の若手男性社員が『もう、ダメです』とすぐに心が折れてしまうことが多くありました。しかし、彼らをコールセンター業務に送り込むと、なぜか元気になって帰ってくるんですよ。
それは、正社員になったお母さんたちが、彼らを下の名前で呼んで、叱りながらも、たくさん褒めてくれるから。営業をやっていたら、叱られてばかりだった若手の男性社員は、彼女たちとの関わりのなかで少しずつ自信を取り戻していったんです」
これを皮切りに、インターゾーンの働き方の多様化は、フルタイムの社員にまで広がっていきます。
自分でやるからこそ気づく。社員はめまぐるしいほどに変化していった

入社5年目で管理部のリーダーである武井優は、週1日は税理士事務所で働いています。
鏡山 「彼は入社 5年目の管理部のリーダー。もともと自分でいろんなことを経験したいタイプ。4年目になったとき、週 1日でもほかの会社で挑戦したいと相談をしてきました。優秀なやつなので、インターゾーンの勤務は 4日間にして、他社の経験を積ませたほうがいいじゃないと思ったんです」
武井は今、税理士事務所にてアナログで行なってきた業務のオンライン化にチャレンジしています。
こうした外で学んだいろんな知見や、新しい仕組みをインターゾーンに持ち帰ってくることもあります。本業を短時間でやらなければならないリスクを背負ってでも、ふたつの会社で働くことで得られる経験は、彼の視野を広げています。将来的には、マンパワーに頼る税理士業界をクラウド化で変えていきたいという意志も芽生えていきました。
また、webディレクターとして5年のキャリアを持つ中途入社の前澤佳奈は、副業でライターをはじめました。
鏡山 「彼女は仕事に行き詰まっていて、ほかのキャリアを考えだしていたので『どうせならライティングの専門を目指したらどうだ』とアドバイスをしました。週 4で Webのディレクション業務や、インサイドセールス業務を行ないつつ、今は週に 1日ライターとして動きはじめています。
彼女は、外に出たことで変わっていったんです。そもそも仕事が 0の状況からはじめたので、ひとりで仕事をとってくる大変さと、チームのありがたさに気づいたと僕に打ち明けてくれました。
彼女からそのような言葉が出てきたことに、正直驚きました。自分で動いてみて、実体験を伴ったからこそ気づいてくれたのだと思います」
今までは、お客さんからWebのディレクション業務のなかで「プロからのアドバイスが欲しい」と言われることがあっても、彼女自身の中では「プロというほどでもないんだけどな……」という思いもありました。でも、会社であれ個人であれお金をもらっている以上、プロでなきゃいけないという意識も生まれたようです。普通に企業でサラリーマンをやっているだけでは、その感覚はなかなか根付きづらいものです。
コールセンターで働くアルバイトスタッフを正社員化するだけでなく、フルタイムの社員の相談に応えるように、働き方を進化させてきたインターゾーン。しかし、最初からそのように柔軟に考えられていたわけではないといいます。
「変わらないといけないのは、僕たち、創業メンバーでした」

鏡山 「今から 3年ほど前、しっかり頑張って働いていた新入社員が、突然辞めてしまったことがありました。後で聞いた話ですが、実はその子が入社する前に父親が亡くなり、母親が祖母の面倒をみていたそうです。彼女は当時めちゃくちゃ働いていて、実家にはあまり帰れていませんでした。
辛い状況だった母親から色々と言われていたそうです……。そんなことが起こっていたなんて、まったく知りませんでした。ただ一生懸命頑張っていると思ってしまっていたんです。
彼女が『辞めたい』と口にしたときには相当追い込まれていたはず。僕は本当の声を拾えていなかったと思いました。そういう声をちゃんと拾わないといけない。彼女の退職以降、半年に1回、社員と面談をするようになり、みんなの話を聞きながら、僕自身が変わっていけるように努力しています。
時代も変わり、会社も成長するなかで、変わらないといけないのは僕たち、とくに創業メンバーでした。社員の声を聞いたときに『こいつ、何もわからないやつだな』と捉えるのか『そういう風にも考えられるようになったのか』と捉えるのか。それだけでも全然違うはずです」
ベンチャー企業を立ち上げ、時間関係なく働いてきた鏡山の考えを変えたのは、社員の生の声でした。
見えてきた働き方改革の本質と、これからの展望

鏡山 「周囲の社員から『この子はちょっと』と言われてしまう子はいます。仕事はきっちりやってくれているので、アルバイトとしては働いてもらいたい。けれども社員化で落とされちゃうと、「私は認められていない」と感じ、そのまま退職してしまうケースもあります」
さらには、週4勤務の社員の部署は、勤怠管理や、給料計算などの労務的問題や、顔を付け合わせて行なう会議の曜日が限られてくるなど、マネジメントにおいても複雑になります。
鏡山 「みんなで残業を減らすのであれば、やりやすい。でも一部の社員が、時短や副業をする場合、そうではないフルタイムの社員に理解してもらう必要があります。なんでそうなのか、理由を少しずつ伝えていく、地道な活動が大切です」
試行錯誤をつづけるなかで、鏡山は、「働き方改革のその本質は、二者択一ではない選択肢を持つこと」と考えるようになったと語ります。
鏡山 「昔の日本は終身雇用で右肩上がり、自分の人生を全部捧げる働き方が一般的でした。給料がどんどんあがる保証もありました。でも今はその保証も存在しないなかで、会社と個人の関係性は旧態依然としています。
さらに昔に比べて牧歌的ではなくて、成果を問われる実態になっています。ゆとりがなく、追い込まれてしまうからこそ、続けるか辞めるかという二択しかないと考えてしまうんです。
仕事には必ず波があるので、複数のコミュニティを持つことで、人間バランスがとれると思います。続けるか、辞めるのか二者択一ではない。それが働き方改革の本質だと思うんです」
今はまだ、踏み込み切れてはいないものの、最終的には誰もが働き方を選べる形にしたいと鏡山は話します。多様な働き方の成功体験を地道に重ねてきたインターゾーンだからこそ、その未来はきっと近いうちに実現できると信じています。